太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。
ご希望の日本の城情報を無料で検索できます。

佐々成政と城
「佐々成政」(さっさなりまさ)は、1536年(天文5年)頃から1588年(天正16年)5月14日にかけて生きた戦国武将です。


![]()
- 小
- 中
- 大
「佐々成政」(さっさなりまさ)は、1536年(天文5年)頃から1588年(天正16年)5月14日にかけて生きた戦国武将です。戦国時代から安土桃山時代にかけての大名であり、1582年(天正10年)には富山城の城主を務めた佐々成政は、「徳川家光」正室の外祖父としても知られています。「織田信長」や「羽柴秀吉」に仕えた武将でもありました。織田信長に見いだされ、小丸城(福井県越前市)の築城を含めて数多くの功績を残した佐々成政ですが、その最期は羽柴秀吉の命令による切腹でした。悲劇的な最期を遂げた佐々成政は、どのような生涯を送ったのでしょうか。
ここでは、佐々成政の生涯について、北陸部隊として同時期に活躍した「前田利家」や「さゆり姫」との関係、さらに「さらさら越え」やゆかりのある城についてご紹介します。
佐々成政の生涯
佐々成政は「佐々成宗」(さっさなりむね)の三男として、「尾張国」(現在の愛知県西部)の「比良城」(名古屋市)にて誕生。生誕年については1512年(永正9年)~1539年(天文8年)の間で諸説あり、定かではありません。

1550年(天文19年)には織田信長に仕えます。兄には「佐々正次」(さっさまさつぐ)と「佐々孫介」(さっさまごすけ)がいましたが、相次いで戦死。そこで、1560年(永禄3年)、佐々成政が25歳で家督を継ぎ、比良城の城主となりました。翌1561年(永禄4年)には、「森部の戦い」で敵将を討ち取る大手柄を立て、1567年(永禄10年)、織田信長の親衛隊の中でも精鋭とされる黒母衣衆(くろほろしゅう)の筆頭を務めています。
母衣とは、兜や鎧の背に巾広の絹布を付けて風で膨らませ、矢や石などから防御する甲冑(鎧兜)の補助武具のこと。織田信長は直属の家臣の精鋭部隊である「黒母衣衆」と「赤母衣衆」を従えており、それぞれ黒と赤に染めた母衣を背負わせました。特に優れた者を選抜していたため、佐々成政が織田信長に評価されていたことがうかがえます。
その後も、織田信長の主要な戦いに臣従。1575年(天正3年)の「長篠の戦い」では3,000人の鉄砲隊の指揮を執る鉄砲奉行を任されました。
同年9月、織田信長は「柴田勝家」を北陸方面の郡団長に任命。そして、「越前国」(現在の福井県北東部)12郡のうち府中近辺の2郡を佐々成政・前田利家・「不破光治」(ふわみつはる)に与えました。この3人を指して「府中三人衆」と呼びます。佐々成政は「小丸城」(福井県越前市)を築いて居城とし、府中三人衆として北陸での戦いに参加。戦いが落ち着いた際には畿内での石山合戦への参戦、織田信長に対して謀反を起こした「荒木村重」(あらきむらしげ)の討伐や荒木一族の処刑を命じられています。
1577年(天正5年)には「手取川の戦い」に参加し、柴田勝家らとともに上杉勢を攻めようとするも惨敗。しかし、半年後に「上杉謙信」が死去したことで形勢は逆転し、1580年(天正8年)には柴田勝家が「加賀国」(現在の石川県南部)を平定し、佐々成政もそれに従い「能登国」(現在の石川県北部)や「越中国」(現在の富山県)に進出しました。これ以降、佐々成政は越中国平定のため、一向一揆や上杉家に対抗。1581年(天正9年)には「富山城」(富山県富山市)を居城とし、大規模な改修を行いました。
絶好調に思えた矢先の1582年(天正10年)、「本能寺の変」により主君である織田信長が無念の死を遂げます。当時、佐々成政はちょうど「魚津城」(福井県越前市)を攻略したところ。織田信長横死の知らせを受けた佐々成政や前田利家は、それぞれの領地へ戻ります。そんななか、羽柴秀吉は「中国大返し」によって畿内へ戻り、「山崎の戦い」で「明智光秀」を討ち取りました。柴田勝家からすると、羽柴秀吉に仇討ちの先を越された形だったのです。その後の「清州会議」(きよすかいぎ:織田家の後嗣問題及び領地再分配に関する会議)において、柴田勝家と羽柴秀吉の対立が表面化。佐々成政は柴田勝家側に付きます。しかし、翌1583年(天正11年)4月、「賤ヶ岳の戦い」(しずがたけのたたかい)で敗北した柴田勝家は、体制を整えようとするも「北ノ庄城の戦い」(きたのしょうじょうのたたかい)で自害となりました。そして、佐々成政は豊臣秀吉に降伏します。上杉家との戦いに備えていたため賤ヶ岳の戦いに参加しなかった佐々成政は、人質を出すことで、それ以上のお咎めはなかったのです。
1584年(天正12年)には「小牧・長久手の戦い」が勃発。織田信長の子である「織田信雄」(おだのぶかつ)・「徳川家康」連合軍と羽柴秀吉軍の戦いです。この戦いで佐々成政は徳川家康側に寝返ります。佐々成政は、羽柴秀吉側に就いていた前田利家の「末森城」(名古屋市千種区)を包囲しましたが、敗走。その後、小牧・長久手の戦いは、豊臣秀吉と織田信雄の間で和議が成立し、徳川家康も停戦します。佐々成政は徳川家康に抗戦を続けるよう、北アルプスを越えて説得に行くも失敗。越中へと帰還しました。
佐々成政はそれでも反羽柴秀吉の姿勢を取り続けます。そんな佐々成政に対し、1585年(天正13年)、羽柴秀吉は佐々成政が居城とする富山城を包囲。佐々成政は降伏し大坂に移住させられ、羽柴秀吉の下で御伽衆として仕えることになりました。御伽衆とは、大名や側近の話し相手のような役割です。
1587年(天正15年)、九州征伐における活躍から、佐々成政は「肥後国」(現在の熊本県)を与えられ、大名に復帰。羽柴秀吉は佐々成政に対し、3年間、田畑を測量して石高などを検査する検地の禁止や、一揆防止などの条件を与えました。しかし、佐々成政は検地を強行。その結果、国人の強い反発を受け、「肥後国人一揆」が起きてしまいました。佐々成政はこれを単独では抑えられず、「立花宗茂」(たちばなむねしげ)らの協力を受けて鎮圧します。
翌1588年(天正16年)、佐々成政は謝罪のために大坂へ向かい、羽柴秀吉に対して面会を求めましたが、羽柴秀吉はこれを拒否。臨済宗の僧「安国寺恵瓊」(あんこくじえけい)が助命を願い出るも聞き入れられず、切腹させられこの世を去りました。辞世の句は「このごろの 厄妄想を 入れ置きし 鉄鉢袋 今やぶるなり」。切腹の際、臓腑をつかんで天井に投げつけたという逸話も残っています。佐々成政の無念と並々ならない思いがうかがい知れるエピソードです。
佐々成政と前田利家の仲

佐々成政と前田利家は、府中三人衆として織田信長から北陸を任された柴田勝家に仕えており、同世代の2人はライバル関係であったと言われています。
前田利家が若い頃、正室である「まつ」の父の形見でもあった笄(こうがい:髪を掻き揚げて髷を作る装飾的な結髪用具)を、織田信長の茶坊主であった「拾阿弥」(じゅうあみ)に盗まれる「笄斬り」(こうがいぎり)と言われる事件が発生。前田利家は激怒しますが、織田信長は拾阿弥の肩を持ちます。結局、前田利家は拾阿弥を斬り殺し、これがきっかけで出仕停止処分となってしまいました。その際に佐々成政も拾阿弥の味方をしたと言われています。長年敵対していたと明言する記録はありません。しかし、互いに意識し合っていたとされています。
佐々成政と前田利家が対峙した戦としては、「末森城の戦い」が有名です。これは、1584年(天正12年)の小牧・長久手の戦いのなか、9月9日に能登国末森城で行われた攻防戦。末森の合戦とも呼ばれます。末森城は前田領であった加賀国と能登国の国境に位置しており、重要拠点でした。佐々成政は宝達山を越えて坪山砦に布陣、総勢15,000の兵で末森城を包囲。奇襲は成功し、翌日には前田家の家臣「奥村永福」(おくむらながとみ)らが籠城戦を展開しますが依然佐々軍が優勢であり、落城寸前まで追い込みました。しかし、この知らせを受けた前田利家は2,500人の兵とともに出陣。夜の闇に乗じて手薄であった海沿いを進軍し、佐々軍の裏手に回ります。翌明け方に奇襲をかけ、佐々成政は敗北を喫しました。
その後の2人については、佐々成政は羽柴秀吉の命令で切腹。その一方で前田利家は五大老のひとりとして徳川家康に次ぐ勢力を持つに至ります。ライバルであった2人の明暗は、はっきりと分かれる結果となってしまったのです。
佐々成政のさらさら越え(アルプス越え)

佐々成政の逸話の中でも特に有名なのが「さらさら越え」。さらさら越えとは、佐々成正らが真冬に越中国と信州(現在の富山県と長野県)を繋ぐ針ノ木峠(北アルプス)を越えた出来事です。
1584年(天正12年)、小牧・長久手の戦いのなか、羽柴秀吉と織田信雄の間で和議が成立。徳川家康も攻撃を停止します。「浜松城」(浜松市)の徳川家康に対して抗戦し続けるよう説得したい佐々成政。当時、越中国にいた佐々成政にとっては、浜松城へ行くには豊臣秀吉の支配下にない北アルプスを越えるルートを通るしかありません。佐々成政は、この無謀とも思える厳冬のアルプス越えを敢行しました。しかし、徳川家康の説得は失敗に終わります。
ただし、さらさら越えのルートについては、標高2,000~3,000mもある北アルプスを厳冬に徒歩で越えることは不可能であるとの見方から、諸説あるのが実情。立山連峰を超えたとするザラ峠・針ノ木峠ルート、飛騨から安房峠を越えて信州に出るルート、越後経由ルートが挙げられます。
いずれにせよ、厳しい環境であることは間違いありません。佐々成政の並々ならぬ熱意が感じられるエピソードです。
佐々成政とさゆり
佐々成政には、「さゆり」(小百合)という側室がいました。美しいさゆりを佐々成政は寵愛。さゆりは子どもを身ごもります。しかし、誰が言い出したのか、さゆりは他の男と密通しており、お腹の子どもは佐々成政の子ではないという噂が流れました。これを信じた佐々成政は激怒し、さゆりに凄惨な暴力を振るった上、殺害。それだけでなく、彼女の一族も処刑するほどの暴虐ぶりでした。
死の間際、さゆりは佐々成政への恨みの言葉と「立山に黒百合が咲いたら、佐々家は滅亡する」との呪いの言葉を残します。
それ以来、さゆりが殺された神通川では風雨の夜に、女の首と鬼火が出ると言われ、その火は「ぶらり火」と呼ばれました。その場所の近くには、さゆりの霊を鎮めるための祠堂が建立。また、佐々家の子孫である「佐々瑞雄」は、母からユリ科の花を生けるなと言われていたと語っているほどです。

また、佐々成政失脚のきっかけのひとつにもなったとされるエピソードにも、同じく黒百合が関係。御伽衆からようやく大名へと復帰した佐々成政は、自身を推挙したお礼にと、「北政所」(羽柴秀吉の正室)に黒百合を献上しました。珍しい黒百合を大いに喜んだ北政所は、ライバルであった側室「淀殿」に自慢しようと茶会で披露。しかし、その後、淀殿はたくさんの黒百合を取り寄せ、取るに足らない花だと見せつけます。恥をかかされた北政所は、佐々成政が自分以外にも黒百合を送ったと思い、恨みを募らせ羽柴秀吉に悪口を吹き込んだ、というエピソードです。
どちらも後世の創作の可能性が高い話ですが、佐々成政に関連する逸話として現代にまで残っています。
佐々成政に関連する城
佐々成政は尾張国の比良城で生まれ、その後小丸城、富山城へと居城を移します。激動の人生を歩んだ佐々成政とゆかりの深い城とはどのような城だったのでしょうか。ここでは、佐々成政にかかわる城の歴史やエピソードについてご紹介します。
比良城(ひらじょう):名古屋市
比良城は尾張国春日井郡比良にあった平城であり、佐々成政の生誕地。
1532年(天文元年)~1555年(天文24年)の天文年間に、佐々成政の父・佐々成宗によって築城されました。現在の光通寺(名古屋市西区)が城跡だと伝わっています。
1575年(天正3年)に佐々成政が越前府中に移ることに伴い廃城。比良城跡には、佐々成政城址の碑と成政の墓が建てられています。
また、比良城の近くには蛇池という池が存在。この池に大蛇がいるという噂を聞いた織田信長が潜ったと伝えられています。家来や農民を集めて水をかき出して探しましたが、結局大蛇は見つかりませんでした。蛇池に訪問した際、織田信長は比良城も見物しようとしましたが、結局寄らずに「清洲城」(愛知県清須市)に直帰。実はこのとき、佐々家の家老「井口太郎左衛門」が織田信長の暗殺を目論んでいました。当時、佐々成政が織田信長に対して逆心を抱いているとの噂が流れており、織田信長が切腹を命じるのではないかと家臣が案じたうえでの目論見です。織田信長がすんでのところで難を逃れたというエピソードでした。
小丸城(こまるじょう):福井県越前市

小丸城は、1575年(天正3年)、鞍谷川によってできた扇状地の丘陵に築城した平城。本丸や土塁などの遺構が残っています。織田信長の命により佐々成政が築城しましたが、1581年(天正9年)には佐々成政が越中国に移封となったため、そのまま廃城。小丸城は完成しなかったという説もあります。
また、1932年(昭和7年)には小丸城跡から文字が書かれた瓦が出土。そこには、一向一揆の際に前田利家によって行われた残忍な処刑の様子を後世に伝えるとの内容が書かれていました。この瓦自体の真偽のほどは定かではありません。もし本物なら、小丸城築城の際に参加した者のなかに、一向一揆から逃げ延びた人物がいたのではないかと言われています。
富山城(とやまじょう):富山県富山市

富山城は梯郭式の平城。梯郭式の利点は、本丸の背に崖や川があり、本丸の出入り口に二の丸、二の丸の出入り口に三の丸と縄張を展開するため、高い防御性を誇ります。富山城は神通川を防御として利用しており、水に浮いているように見えたために「浮城」と呼ばれ、難攻不落の城と言われていました。1543年(天文12年)、「神保長職」(じんぼうながもと)が命じて築城したと伝承。しかし、発掘調査で室町時代前期の遺構が発見されたことから、築城はそれ以前であると考えられています。
数々の城主が入れ替わったあと、1582年(天正10年)に佐々成政が城主となりました。佐々成政は、堀をより深くし土塁や石垣を高くするなど、大規模改修を実施。「本能寺の変」後に羽柴秀吉と対立した佐々成政は、1585年(天正13年)、羽柴秀吉の軍勢10万人に富山城を囲まれて降伏し、城は破却されます。その後は前田利長が富山城を再建し隠居城としましたが、火事で焼失。そのまま前田家が治め、江戸時代には幕府の許しを得て本格的に修復されました。
1871年(明治4年)、廃藩置県により富山城は廃城となります。本丸御殿は県庁舎として、二の丸二階櫓御門は小学校として利用されることになりました。しかし、その後も2度火事で焼失。1954年(昭和29年)に富山産業大博覧会が開催され、鉄筋コンクリート造の模擬天守が建てられることになり、翌年完成。現在は富山市郷土博物館となっています。
魚津城(うおづじょう):福井県越前市
魚津城は、1335年(建武2年)に椎名孫八入道によって築城されたと伝承。戦国時代に上杉氏によってその支配下に置かれ、重要拠点となりました。1582年(天正10年)の「魚津城の戦い」では、織田軍と上杉軍の攻防戦の舞台となり、織田軍に包囲されるなかで籠城戦を展開するも織田軍が勝利。魚津城は落城します。
しかし、本能寺の変で織田信長が横死した知らせを受け、織田軍は撤退。空になった魚津城には上杉軍が入り、奪還します。しかし1583年(天正11年)に佐々成政が再度侵攻したことで、魚津城は開城されました。
その後は前田家が統治。しかし、元和の一国一城令によって廃城となりました。現在は小学校や裁判所の敷地となっており、遺構はほとんど残っていません。
末森城(すえもりじょう):名古屋市
佐々成政 10代の頃から「織田信長」に仕え、戦いに明け暮れた佐々成政の生涯について、数々の逸話や伝説と共に振り返り、剛胆かつ実直な人物像をご紹介します。
刀剣特集
日本のお城(城郭)に関する様々なお役立ちコンテンツをご紹介します。

歴史を動かした有名な戦国武将や戦い(合戦)をご紹介!

戦国の世を生き抜いた戦国武将の合戦戦略について
解説します。
武将・歴史人のエピソードや、関連のある日本刀(刀剣)をご紹介!

戦国武将の中でも「戦国三英傑」と呼ばれる織田信長、豊臣秀吉、徳川家康についてご紹介します。

日本刀が大活躍した時代にあった主な合戦をご紹介します。

全国各地の古戦場を地域ごとにご紹介致します。

刀剣ワールドで紹介している人気の戦国武将をイラストと合わせて、ランキング形式でご覧頂けます。

歴史上の人物と日本刀にまつわるエピソードをまとめました。
お役立ちコンテンツ
日本のお城(城郭)に関する様々なお役立ちコンテンツをご紹介します。
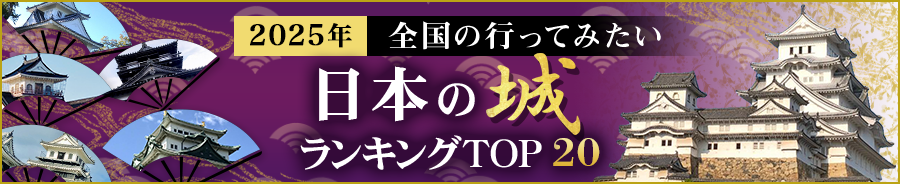
日本の城を訪れた皆さんの声を元に刀剣ワールド/城が選ぶ行って良かった日本の城をランキング形式でご紹介!皆さんからの口コミ情報も掲載中です!
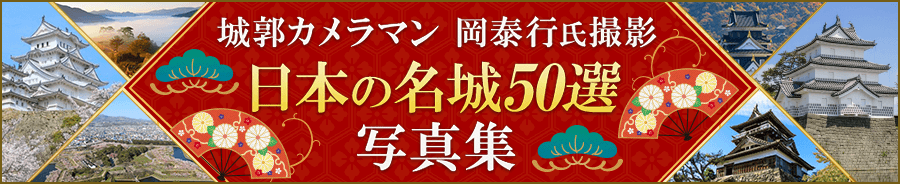
城郭カメラマン・岡泰行氏によって撮影された魅力あるお城の写真をご覧頂けます。

日本の城、城郭、城跡を日本地図から検索できます。基本情報や口コミ、写真、動画が満載で知りたい情報が見つかります!

全国のランキングはもちろん、都道府県や市区町村ごとのランキングをご紹介!

日本全国にある多くの城と、城に縁のある武将をご紹介!

歴史と城を旅する気分で列島縦断クイズに挑戦!
特集コンテンツ
日本のお城(城郭)に関する様々なお役立ちコンテンツをご紹介します。













コメント
コメントを投稿