太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。
- 小
- 中
- 大
「徳川四天王」とは「徳川家康」に仕え、最も重用された4名の戦国武将のことを指します。彼ら徳川四天王は、徳川家康が若く、人質であった頃から支え、生涯に亘って忠義を尽くしました。江戸幕府の開設には、彼ら四天王の支えが必要不可欠だったと言われ、現在でもその名は広く知られています。
徳川四天王とは

徳川家康
「徳川四天王」とは、戦国の世を太平に導き、江戸幕府を開設した初代将軍「徳川家康」に忠義深く仕官し、江戸幕府の基盤づくりに大きな貢献をした4名の武将「井伊直政」、「酒井忠次」(さかいただつぐ)、「榊原康政」(さかきばらやすまさ)、「本多忠勝」のこと。
徳川家康は前途多難な半生を過ごし、天下取りへの道は決して恵まれたものではありませんでしたが、そのうえで天下統一を成し遂げたのは、優れた部下達の働きがあったからだと言えます。
この4名が徳川四天王といつ頃から呼ばれたのかは不明ですが、1586年(天正14年)に徳川家康の名代として、井伊直政、榊原康政、本多忠勝が上洛した際に、彼らが「徳川三傑」と呼ばれ、この3人に徳川家最古参の家臣である酒井忠次を加えた4名が、のちに徳川四天王と呼ばれるようになったとされています。徳川家康の高名な家臣「徳川十六神将」と同じく、四天王と言う言葉は、仏教の守護神である「四天王」を暗示させているのです。
ここでは、「犬のような忠義心」だと敵将から揶揄されたほど、徳川家康に対し厚い忠誠を誓い、その手助けをした徳川四天王に数えられる4名の武将を紹介していきます。
井伊直政

井伊直政
井伊直政は徳川四天王のうち最年少で、「関ヶ原の戦い」後、四天王のなかで最も大きな知行国を与えられた、徳川家康の腹心とも言える武将。
知力があり、外交交渉などでも力を発揮しましたが、戦場では「井伊の赤鬼」と恐れられるほど、苛烈な一面を持つ猛将でした。
井伊直政は、1561年(永禄4年)に、遠江国祝田(とおとうみのくにほうだ:現在の静岡県浜松市)に誕生。井伊直政は徳川四天王のなかで唯一、三河国(現在の愛知県東部)出身の譜代ではなく、元々は今川氏に仕える家系の出身でした。
女城主として知られる「井伊直虎」に養育され、1575年(天正3年)15歳の頃、徳川家康に小姓として仕え始めます。井伊直政は次々と武功を挙げ、「本能寺の変」ののちは、武田家の遺臣を直属の部下とすると、徳川家康の指示で「武田の赤備え」を「井伊の赤備え」として継承。「赤備え」とは、全身の武装を赤一色で揃えることを言い、戦場で一際目立つ赤色は、武勇に秀でた象徴とされ、多くの敵軍を恐れさせました。
1584年(天正12年)の「小牧・長久手の戦い」で、この赤備えを身にまとい、獅子奮迅の活躍をした井伊直政は、敵から井伊の赤鬼と恐れられるようになったのです。
関ヶ原の戦いでは持ち前の外交手腕を発揮し、多くの武将を東軍の味方に付けることに成功します。井伊直政は、この戦いで受けた傷がもとで亡くなることとなりますが、関ヶ原の戦いののち、西軍の大将である「毛利輝元」(もうりてるもと)との講和等の戦後処理や、江戸幕府の基礎を固めるために奔走。はじめは「石田三成」の旧領18万石が与えられましたが、そののち彦根藩30万石の初代藩主となりました。
酒井忠次

酒井忠次
酒井忠次は、徳川家康の父「松平広忠」(まつだいらひろただ)の頃から仕官し、徳川家康が今川家の人質となった際も同行した、生涯を通して徳川家康を支えた武将のひとりです。
忠義を尽くす三河武士らしく、数々の困難が降りかかった若い徳川家康を支え、徳川四天王・徳川十六神将共に筆頭と呼ばれています。
酒井忠次は1560年(永禄3年)の「桶狭間の戦い」ののち、徳川家の家老となり、「姉川の戦い」や「三方ヶ原の戦い」、「長篠の戦い」など、多くの合戦で武功を挙げ、徳川家康に貢献。「三河一向一揆」では、酒井氏の親族が浄土真宗の一揆側に付いたのに対し、徳川家康側に付き従って戦い、その忠義深さを示しています。
また「神君伊賀越え」と共に、徳川家康の最大の危機と言われる三方ヶ原の戦いでは、徳川家康が無事に「浜松城」(現在の静岡県浜松市)へ敗走したのち、酒井忠次は残された軍の士気を高めるため城の櫓で太鼓を高らかに打ち鳴らし、数多くの伏兵がいると考えた敵軍を退却させました。この逸話は、「酒井の太鼓」として後世にまで伝えられています。
酒井忠次は1596年(慶長元年)に死去したため、主君・徳川家康が天下人となった世を見ることができませんでしたが、初期から徳川家康を支えた忠義に厚い最古参の武将でした。
榊原康政

榊原康政
榊原康政は、松平家(徳川家康の実家)の陪臣(ばいしん:臣下である者の、そのまた臣下)である榊原家に次男として誕生。
幼い頃から勉学に秀で、13歳の頃に徳川家康直属の小姓として仕え始めます。
榊原康政は徳川家康の転機とも言える三河一向一揆で初陣を飾ると、徳川家康に武功を認められ、「康」の偏諱(へんき:将軍などが自分の名の1字を与えること)を賜りました。
姉川の戦いでもその武勇は発揮され、本多忠勝が単騎で朝倉軍をかく乱させるのを確認すると、側面攻撃を仕掛けて朝倉軍を撤退させることに成功。また、三方ヶ原の戦いでは、徳川家康が浜松城に退却するのを見届けると、自身は城内に入らずに追撃を仕掛ける武田軍と交戦し、武田軍を瓦解させました。
このように、忠義深く武勇に優れた三河武士らしくその力を発揮し、徳川家康が「豊臣秀吉」によって関東に移封されると、本多忠勝と並び、家中で第2位の石高を与えられています。
なお、榊原康政は豊臣秀吉に10万石の懸賞金をかけられたこともあるほど、豪胆な人柄であったとも。「武備神木抄」には、武勇では本多忠勝に劣るものの、部隊の指揮官としては井伊直政と並ぶほど優れていたと伝えられました。
この井伊直政とは歳がひと回りほど離れていましたが、親しく交友していたと言われ、井伊直政の死後、まだ幼い嫡男「井伊直孝」(いいなおたか)に何かあったら自分に伝えるように書いた書状が残されています。
本多忠勝

本多忠勝
本多忠勝は、その武勇で「戦国最強」のひとりに数えられる、徳川家康の忠臣として有名な武将。
井伊直政が重装備で出陣し、毎回負傷して帰還していたのに対し、本多忠勝は軽装備で出陣するも毎回無傷であったことは有名な話。本多忠勝は生涯に亘る57回の戦闘で、かすり傷ひとつ負わなかったと言われています。
本多忠勝の戦場での働きはあまりにもすさまじく、姉川の戦いで追い込まれた徳川軍の突破口を開くため、本多忠勝は単騎駆けを行ない、朝倉軍のかく乱に成功。
三方ヶ原の戦いの敗走で、殿(しんがり:軍の最後尾で敵の追っ手を食い止めること)を務めた際に起こった「一言坂の戦い」(ひとことざかのたたかい)では、徳川家康を無事に撤退させるまで奮戦する等、その勇名を全国に轟かせ、「蜻蛉が出ると、蜘蛛の子散らすなり。手に蜻蛉、頭の角のすさまじき。鬼か人か、しかとわからぬ兜なり」と本多忠勝の武勇を称えた川柳が詠まれました。この「蜻蛉」とは、本多忠勝が愛用していた、天下三名槍のひとつに数えられる槍「蜻蛉切」のこと。
また、徳川家康と豊臣秀吉が対決した小牧・長久手の戦いでは、僅か500騎の兵を率いて豊臣軍数万の兵と対峙するなど、本多忠勝の武勇伝には枚挙に暇がありません。神君伊賀越えでは自害を覚悟する主君に対し、一喝して奮い立たせる等、いざというときに諫言ができる信頼の厚い家臣でした。
関ヶ原の戦いののちは一転、戦乱の時代が終わり幕政の表舞台に立つことはなくなりましたが、臨終の際にも主君を残して先に死ぬことを口惜しく思う旨の辞世の句を残したのです。

徳川四天王をSNSでシェアする





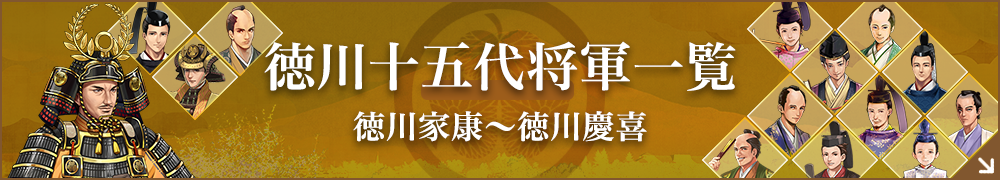











コメント
コメントを投稿